国税徴収法が学べるオンライン講座まとめ
国税徴収法のオンライン講座は種類が多く、特徴もさまざまです。この記事では、国税徴収法を開講しているオンライン講座について、費用や学習スタイル、サポート内容などを紹介しています。
国税徴収法が受講できるオンライン講座一覧
ここでは、「税理士 オンライン講座」のGoogle検索結果、上位10ページで確認できた税理士オンライン講座の初学者向けコースを紹介しています。(2025年3月調査時点)
ネットスクール
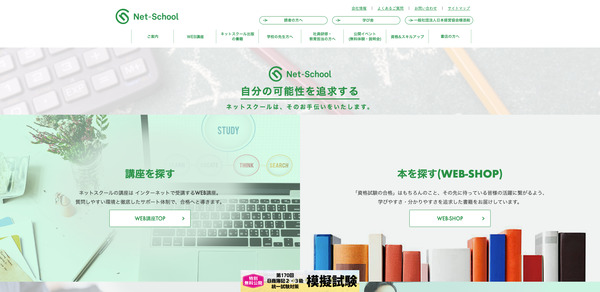
2025年度 国税徴収法標準コース
| 料金 | 77,500円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者・学習経験者向け |
| 開講スケジュール | 8月開講 |
| 学習期間 | 12ヶ月 |
講座の特徴
標準講座は、法律の理解を深める基本講義に加え、実務に即した問題演習や直前対策まで一貫してカバー。知識をインプットする「インプット講義」と、演習を通じて理解を深める「アウトプット講義」に分かれており、段階的に実力を養える構成です。
現行制度にアレンジした過去問対策や、出題傾向に基づく「的中答練」も用意されており、合格に向けた総仕上げが可能。毎月の確認テストや、Zoomを利用した個別コンサルなど、継続的な学習を支えるフォロー体制も整っています。
また、学習経験者を対象とした、過去問ゼミと答練をセットにした直前対策コースは、アウトプットに特化したカリキュラムとなっており、受験対策の総仕上げに適しています。
ネットスクールの口コミ
- 2021年度・国税徴収法 合格
実際に講義を受けてみると、これまで理解が不完全だった「なぜこうなるのか」がすっきりと理解でき、まさに目からウロコが落ちる、という体験でした。(中略)
「ラストスパート模試」は過去8年分と模擬試験4回分が収録されていましたので、これだけでも練習量としては充分だったと思います。答案の書き方自体もあまりよく知らず、以前は隙間なくビッシリと書いていましたので、適度にスペースを空ける書き方を教えてもらったことも受講してよかった、と思いました。
資格の学校TAC

8月・9月 基礎マスター+上級コース
| 料金 | 160,000円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 8月・9月入学 |
| 学習期間 | 記載がありませんでした。 |
講座の特徴
年内に税理士試験の得点源となる基本事項の習得を進め、12月下旬からは上級講義で基礎内容の再確認と応用論点の学習を行います。上級演習では、講義と並行して知識の習熟度を確認し、解法手順の定着を図っていく講座です。
学習内容を年内・年明け・直前期の3つの段階に分けて繰り返すことで、出題頻度の高い論点の理解と定着を促すカリキュラムです。
資格の学校TACの口コミ
- 2024年度・国税徴収法 合格
講義もわかりやすく、質問電話をしたときもものすごく丁寧に長い時間対応してくださったこと。通信講座で提出したテストが返却された時、採点した方からの心強いコメント。自習室を使うために通っていた校舎の方々の丁寧な対応や綺麗な自習室。
これら全ての要素があったことで、日々の勉強に力が入り、合格することができました。ありがとうございました。
資格の大原

9月開講 初学者一発合格コース
国税徴収法
| 料金 | 152,000円(税込)(教材費不明) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 9月開講 |
| 学習期間 | 記載がありませんでした。 |
講座の特徴
大原の「初学者一発合格コース」は、忙しい社会人でも取り組みやすい年間設計が特長です。年内に本試験出題項目の60〜80%をカバーし、基礎期・応用期を通じて2回転の学習が可能なカリキュラムを採用。
無理のないペースで進めながら、重要項目の理解を着実に深められる構成となっており、初学者でも経験者と同等の実力を養うことができます。
資格の大原の口コミ
- 国税徴収法 合格
通信講座でお世話になりました。今年合格することができました!先生の時間配分のお話がとても役に立ちました。時間配分を考えていなければ第一問に時間をとられて第二問が解けていなかったと思います。
本試験中は難しくて諦めそうになりながらもなんとか踏ん張れました。先生の授業で教わった、考えながら暗記することもとても役に立ちました。今年はベタ書きが少なかったので何も考えずに暗記だけしていたら太刀打ちできなかったと思います。先生の熱い授業とzoomのスタディーサポートのおかげで合格できました!本当にありがとうございました!!
講座選びの前に押さえておきたいポイント
ここまで国税徴収法が学べるオンライン講座を紹介してきましたが、各講座によって特徴や進め方に違いがあります。ご自身の目的や学習の進め方に合わせて、無理のない講座を選ぶことが大切です。
このサイトでは、税理士試験を受ける方の「仕事と両立しながら合格したい」「3年で短期合格を目指したい」「大学院の科目免除を活用したい」という3つのニーズに合ったオンライン講座を紹介しています。合格を目指してオンライン講座を探している方は、ぜひ参考にしてください。
国税徴収法の試験について
国税徴収法とは?
国税徴収法は、国税を滞納した場合の徴収手続きや、財産差押・換価などの執行に関するルールを学ぶ科目です。実務に直結する知識が多く、徴収行政の基本的な考え方や法律の適用を理解することが求められます。
試験内容
国税徴収法の試験は、理論問題と計算問題の2つで構成されており、合計100点満点です。
- 理論問題:50点(条文や制度の趣旨、事例に関する記述式)
- 計算問題:50点(滞納処分における換価・配当などに関する計算)
理論では、徴収手続きの流れや差押・換価・配当のルールについての理解を問う設問が出題されます。計算問題では、財産の評価や配当順位の判断など、事例に基づいた処理力が求められるのが特徴です。
合格基準と難易度
国税徴収法の合格基準は、100点中60点以上の得点とされています。ただし、実際の合否は試験の難易度や受験者の成績分布などを踏まえて総合的に判定されます。
条文の理解だけでなく、理論と計算の両方をバランスよく学習することが重要です。
合格率の傾向
国税徴収法の合格率は、2022年度が13.8%、2021年度が13.7%と、比較的安定した水準で推移しています。例年10%台前半であり、他の税法科目と同様に継続的な学習が求められます。
試験の特徴
国税徴収法の試験では、実務に即した出題が多く、条文理解と具体的な事例対応の力が求められるのが特徴です。
理論問題では、徴収手続の流れや優先順位などの理解が問われ、計算問題では財産の配当順位や分配額などを的確に算出する力が必要です。
また、法令の改正や判例にも注目しながら、基礎知識をしっかり身につけ、事例対応力を高めておくことが重要です。
国税徴収法の学習方法
目安の勉強時間
国税徴収法の合格に必要とされる学習時間は、おおよそ500時間以内とされています。他の税法科目に比べて出題範囲のボリュームが比較的少なく、計算問題も多くないため、やや短めの学習時間で済むと考えられています。
とはいえ、これはあくまでも目安であり、基礎から確実に理解を積み上げることが重要です。限られた時間の中でも、丁寧な学習を心がける必要があります。
知識レベルによって学習時間が変わる
法律に関する学習経験がある方や、すでに他の税法科目を学んだことがある方は、条文の構造や税法用語への理解が早く、短期間で実力をつけやすい傾向があります。
一方、税法に初めて触れる場合や法律に苦手意識がある場合は、条文の読み方や徴収手続の流れを理解するのに時間がかかることもあるため、余裕を持った学習計画が求められます。
インプットとアウトプットの
バランスが重要
国税徴収法は理論中心の出題が多く、体系的な理解と条文の正確な把握が鍵となります。まずはインプットを通じて法令の背景や仕組みをしっかり学びましょう。
そのうえで、過去問や答練などを活用しながら、繰り返し演習を行うことで実践力を養っていくことが大切です。限られた時間の中でも、アウトプットの量と質を意識した学習が合格への近道になります。
オンライン税理士講座3選
税理士試験の合格をサポートするオンライン講座を3つご紹介します。あなたの学習スタイルや状況に合った講座を見つけ、官報合格を目指しましょう!
仕事と両立しながら
着実な合格を目指す
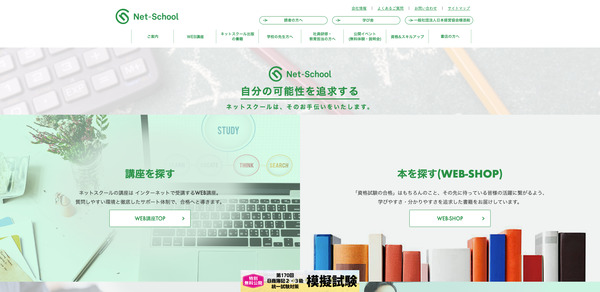 引用元:ネットスクール公式HP
引用元:ネットスクール公式HPhttps://www.net-school.co.jp/
ライブ授業は平日の19:30〜22:00に行われ、通勤・通学の帰りでも受講が可能。チャットで講師に質問し、わからない部分をその場で解決できます。
働きながらでもムリのないペースで学習を進められるよう、会計は1年2科目、税法は1年1科目の合格スケジュールをサポートしています。
勉強時間の集中確保で
3年間での合格を目指す
 引用元:資格の学校TAC公式HP
引用元:資格の学校TAC公式HPhttps://www.tac-school.co.jp/
3度の受験で官報合格を目指す5科目パックを提供しています。1日3〜4時間の学習時間が取れる方や、短期間で合格を目指したい方に向いている講座です。
本試験の傾向を徹底的に分析し、効率を重視した戦略的なカリキュラムを構築。合格に必要な要素だけを厳選し、短期間での合格を目指します。
科目免除を利用して
短期合格を目指す
リーガルマインド
 引用元:LEC東京リーガルマインドHP
引用元:LEC東京リーガルマインドHPhttps://www.lec-jp.com/
提携するLEC会計大学院の科目免除を組み合わせて、短期合格を目指せます。
LEC会計大学院の在学中と修了後2年間は税理士講座が5割免除でお得に受講できます。(※)
※大学院事務局の審査があり、また対象講座および免除率は変更となる可能性があります。