財務諸表論が学べるオンライン講座まとめ
財務諸表論のオンライン講座にはさまざまな種類があり、講座ごとに特徴や費用、学習期間が異なります。この記事では、財務諸表論を開講しているオンライン講座について、受講費用や学習方法、サポート体制などをまとめました。
財務諸表論が受講できる
オンライン講座一覧
ここでは、「税理士 オンライン講座」のGoogle検索結果、上位10ページで確認できた税理士オンライン講座の初学者向けコースを紹介しています。(2025年3月調査時点)
ネットスクール
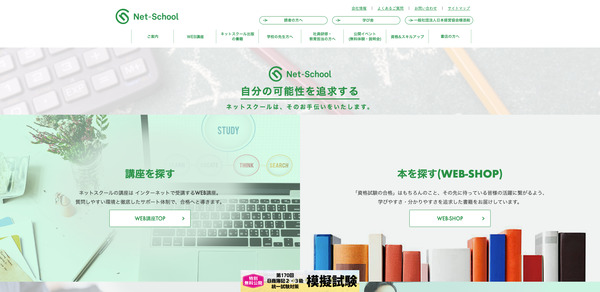
2026年度 財務諸表論標準コース
| 料金 | 145,600円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 8月開講 |
| 学習期間 | 12ヶ月 |
2026年度 財務諸表論ゼロ標準コース
この講座は、ネットスクールのWEB講座で直前対策コースを除く、簿記・税理士・建設業経理士などを受講した方が対象です。
| 料金 | 155,000円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 8月開講 |
| 学習期間 | 12ヶ月 |
講座の特徴
ネットスクールの財務諸表論講座は、簿記論と共通する内容を「インプット講義」で効率的に学び、知識を「アウトプット講義」で実践的に定着させる一体型カリキュラムが特長です。
特に「アウトプット講義」では、多くの受験生が苦手とする理論分野に重点を置き、講師との双方向コミュニケーションを取り入れたライブ形式で進行。疑問点をその場で解消しながら、理解を深めていけます。
オリジナルレジュメや問題集も活用し、講義内容と教材がしっかり連動している点もネットスクールならではの強みです。簿記論とあわせて、2科目を無駄なく学べる構成で、学習の効率化を図ります。
ネットスクールの口コミ
- 2019年度・簿記論、財務諸表論 合格
講義について、特に素晴らしかったのは財務諸表論です。理論は「暗記」ではなく「理解」だと教えて頂きました。税理士試験の理論問題は暗記で太刀打ちできる問題は減少傾向にあり、根っこのところを理解できているかが重要になってきています。
先生の講義は一つのテーマを掘り下げて、他のテーマとのつながりをもとに理解を深めていきます。だから知識が抜けにくく、変則的な試験問題にも対応できます。最後は自分の言葉で、会計の知識のない人に説明できるほど理解が深まっていました。
おかげで本番で理論の選択問題をしっかり解答できました。自分の力というよりは、講師の方に合格まで導いてもらったような気持ちです。
資格の学校TAC

5月入学 完全合格+上級コース「財務諸表論」
| 料金 | 235,000円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 5月開講 |
| 学習期間 | 15ヶ月 |
講座の特徴
2026年の合格を目指し、着実に学習を進められるコースです。年内は知識の定着を重視し、12月下旬からは問題演習中心の実践対策にシフト。基礎から応用まで幅広く対応できる力を養うカリキュラムとなっています。
年内は週1回の講義ペースで、復習の時間をしっかり確保しながら基礎力を固めていきます。12月下旬以降は週2回の講義となり、基本の再確認と応用論点の習得を重ねて、直前期に向けた総仕上げへと進むことができるでしょう。
資格の学校TACの口コミ
- 2024年度・財務諸表論 合格
初めての受験で働きながらの勉強はとにかく不安でしたが、簿記論は自己採点60点超え、財表は合格率8%に入れる合格答案を作れたことは、TACの素晴らしい講義と多くの人のサポート・応援のおかげでした!本当にありがとうございました!
簿記論は、わかりやすい講義のおかげで何年も前にやった日商1級の勉強が蘇ってきて理解が捗りました。理論は最初の頃こそ呪文でしたが、わかりやすい講義で受験前には非常に内容の理解に落とし込めるようになりました。そのおかげで、本試験の簿記論の包括利益の問題が解けたと思っています。今まで頑張ってきたすべての勉強は今に繋がっていると強く感じた受験期間でした。
資格の大原

9月開講 初学者一発合格コース
財務諸表論 Web通信
| 料金 | 225,000円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 5月開講 |
| 学習期間 | 記載がありませんでした。 |
講座の特徴
初学者でも合格レベルまで到達できるよう設計されたカリキュラムです。経験者と同じ水準を目指しながら、講義は最後まで週1回ペースで進行。忙しい社会人でも、自学自習の時間をしっかり確保しながら学習を進められます。
毎回の講義後には、前回内容の理解度を確認する「ミニテスト」を実施。さらに、1ヶ月分の内容を振り返る「確認テスト」も用意されており、段階的に知識を積み上げることができます。
試験直前期には、出題範囲が明確な模擬試験で総復習が可能です。本番に近い環境で練習することで、知識の定着はもちろん、当日の試験にも落ち着いて臨めるようになります。
資格の大原の口コミ
- 簿記論、財務諸表論 合格
分かりやすい授業をありがとうございました。通信でしたが、気持ちを切らすことなく、緊張感をもって勉強し続けることができました。最後の講義で先生が涙ながらにメッセージを伝えてくださって嬉しかったです。
また、私は暗記が苦手だと思い込んでいたのですが、先生の「理論暗記が苦手な人はいない、理論は覚えるまでやる」という言葉のおかげで意識が変わりました。
クレアール

2026年合格目標講座 新・財務諸表論レギュラーコース
| 料金 | 196,000円(税込・教材費込み) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 記載ありませんでした。 |
| 学習期間 | 記載ありませんでした。 |
講座の特徴
新・科目別レギュラーコースは、基礎から応用へと段階的に学び、着実に実力を養うコースです。学習は「基礎期」「応用期」「直前期」の3段階に分かれており、まずは基礎固めからスタートします。
この講座では、クレアール独自の「非常識合格法」を採用。すべてを網羅するのではなく、合格に必要な重要論点に絞って学習するスタイルです。
テキストや問題集も、重要ポイントだけを厳選して構成されているため、内容は非常にコンパクト。繰り返し学習しやすく、何度も問題を解くことで、合格に必要な実力を効率的に身につけることができます。
クレアールの口コミ
- 2024年度・財務諸表論 合格
先生の講義は分かりやすく丁寧なのはもちろんですが、一番記憶に残っているのは、先生が税理士として体験したお話や、実際税理士になってからの心構えや監査のお話です。実務に直結したお話は、非常に興味をもって受講することができました。(中略)
また、すべての教材がPDFで提供されているので、テキストをiPadに入れて、いつでもどこでも勉強ができました。iPad上での書き込みや検索も可能なので、気になる箇所をすぐに検索でき、スムーズに復習ができました。
LEC東京リーガルマインド

2026年度合格目標 簿財横断プレミアムコース
| 料金 | 272,800円(税込)(教材費は不明) |
|---|---|
| 対象者 | 初学者向け |
| 開講スケジュール | 記載がありませんでした。 |
| 学習期間 | 記載がありませんでした。 |
講座の特徴
「簿記論」と「財務諸表論」の同時合格を目指すために、学習効率を追求した講座です。両科目に共通する内容を分析し、重複を省いた講義構成にすることで、勉強時間を大幅に短縮。効率的に学習を進めることができます。
初学者にも安心なのが、プレミアムコースに含まれる「横断演習ブリッジ講座」です。講義で学んだ知識を、演習問題を通じて実践的に活かせるよう設計されており、過去問を参考にした問題も豊富。解法の指導にも力を入れており、演習を通じて確実に実力を養います。
LEC東京リーガルマインドの口コミ
- 2024年度・簿記論、財務諸表論 合格
簿財同時学習を行ったことで大きなシナジー効果を生み、今回の同時合格につながったと思いますので、1科目ずつの学習ではなく簿財横断で学習して良かったなと感じています。(中略)
教材については、簿財横断コースだと基本的に簿記と財務諸表の計算問題は1つの教科書、問題集にまとめられているため、他の予備校のように簿記論と財務諸表論を分冊で持ち歩かなくていいので、非常に良かったです。
講座選びの前に押さえておきたいポイント
ここまで財務諸表論が学べるオンライン講座を紹介してきましたが、各講座によって特徴や進め方に違いがあります。ご自身の目的や学習の進め方に合わせて、無理のない講座を選ぶことが大切です。
このサイトでは、税理士試験を受ける方の「仕事と両立しながら合格したい」「3年で短期合格を目指したい」「大学院の科目免除を活用したい」という3つのニーズに合ったオンライン講座を紹介しています。合格を目指してオンライン講座を探している方は、ぜひ参考にしてください。
財務諸表論の試験について
財務諸表論とは?
財務諸表論は、企業の財務情報を正しく表示・分析するための、財務諸表の作成ルールや背景にある会計理論を学ぶ科目です。帳簿に記録された情報をどのように開示するかを学ぶ内容で、税理士試験における会計2科目のひとつです。
試験内容
財務諸表論の試験は、第一問と第二問で構成される「理論問題」と、第三問の「計算問題」の2分野で構成されています。
合計100点満点として、合格基準点は満点の60%。出題形式は次のとおりです。
- 理論問題:50点(会計基準や財務諸表の意義などを問う記述式)
- 計算問題:50点(帳簿や決算整理などの数値処理)
計算問題は簿記論と似た形式ですが、財務諸表論では理論問題が大きな比重を占めているのが特徴です。出題範囲には、最新の会計基準や改正論点が含まれることもあり、日頃の情報収集と理解の深さが求められます。
合格基準と難易度
財務諸表論は、財務諸表の作成方法やルール、理論などを学ぶ科目です。財務諸表とは、企業の経営状況や財産状況を開示・報告するための資料を指します。
試験は100点満点で構成され、合格するためには60点以上の得点が必要とされています。ただし、60点を取れば必ず合格できるとは限らず、その年の難易度や受験者数などによって合格基準が変動することがあります。
合格率の傾向
財務諸表論の合格率は、2022度が14.8%、2021年度が23.9%と、年度によってばらつきがあります。とはいえ、他の科目と比較すると合格率は高めと言えるでしょう。今後も合格率の動向には注目が必要です。
試験の特徴
財務諸表論の試験は、第1問・第2問が理論問題、第3問が計算問題という構成が一般的で、配点はそれぞれ25点・25点・50点となっています。
理論問題では会計基準や財務諸表の意義などについての理解が問われ、計算問題では帳簿処理や決算整理などの実務的な対応力が求められます。理論と計算の両面からバランスよく問われる点が特徴です。
財務諸表論の学習方法
目安の勉強時間
財務諸表論の合格までに必要とされる学習時間は、おおよそ450~600時間とされています。ただし、これはあくまで目安であり、事前にどれだけ簿記などの知識を持っているかによって、必要な時間は大きく変わってきます。
簿記の基礎がある場合は、スムーズに学習を進められ、勉強時間を短縮できる可能性もあります。一方、知識が不十分な場合や基礎からやり直す必要がある場合は、より多くの時間を確保してじっくり取り組む必要があるでしょう。
知識レベルによって学習時間が変わる
すでに簿記1級や2級の知識を持っている場合は、計算問題にスムーズに取り組めるため、比較的短時間での合格も目指せる可能性があります(おおよそ400時間前後)。
一方で、簿記の基礎知識がない方や、学習から期間が空いている方は、まずは簿記2級程度の基礎力を固める必要があります。そのため、600時間以上の学習時間が必要となるケースもあります。自分の理解度に応じて、無理のない計画を立てることが大切です。
よく出る出題範囲と対策のポイント
財務諸表論では、前述のとおり理論問題と計算問題の両方が出題されます。
理論問題は、会計の基本的な考え方や制度の趣旨などを問う設問が中心で、穴埋め・選択式・論述式など多様な形式で出題される傾向があります。
計算問題では、会社法などに基づく財務諸表の作成力が求められる内容が中心です。
理論問題の対策としては、単なる丸暗記ではなく、会計原則や制度の背景についての理解を深めることが重要です。計算問題に関しては、正確な計算力と財務諸表作成スキルを磨くことがポイント。繰り返し問題を解き、実践力を養っていきましょう。
簿記論と財務諸表論は
まとめて学習した方が良い?
可能であれば、財務諸表論と簿記論は並行して学習することをおすすめします。
財務諸表論は税理士試験の必須科目であり、もう一つの必須科目である簿記論とは、学習範囲や計算方法に多くの共通点があります。両方を同時に学ぶことで、それぞれの理解が深まり、効率よく知識を定着させることができます。
併行学習により、重複する内容を一度の学習でカバーできるため、全体の勉強時間を抑えつつ、試験対策を効果的に進めることができるでしょう。
オンライン税理士講座3選
税理士試験の合格をサポートするオンライン講座を3つご紹介します。あなたの学習スタイルや状況に合った講座を見つけ、官報合格を目指しましょう!
仕事と両立しながら
着実な合格を目指す
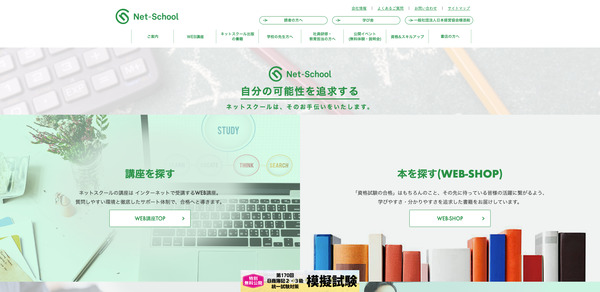 引用元:ネットスクール公式HP
引用元:ネットスクール公式HPhttps://www.net-school.co.jp/
ライブ授業は平日の19:30〜22:00に行われ、通勤・通学の帰りでも受講が可能。チャットで講師に質問し、わからない部分をその場で解決できます。
働きながらでもムリのないペースで学習を進められるよう、会計は1年2科目、税法は1年1科目の合格スケジュールをサポートしています。
勉強時間の集中確保で
3年間での合格を目指す
 引用元:資格の学校TAC公式HP
引用元:資格の学校TAC公式HPhttps://www.tac-school.co.jp/
3度の受験で官報合格を目指す5科目パックを提供しています。1日3〜4時間の学習時間が取れる方や、短期間で合格を目指したい方に向いている講座です。
本試験の傾向を徹底的に分析し、効率を重視した戦略的なカリキュラムを構築。合格に必要な要素だけを厳選し、短期間での合格を目指します。
科目免除を利用して
短期合格を目指す
リーガルマインド
 引用元:LEC東京リーガルマインドHP
引用元:LEC東京リーガルマインドHPhttps://www.lec-jp.com/
提携するLEC会計大学院の科目免除を組み合わせて、短期合格を目指せます。
LEC会計大学院の在学中と修了後2年間は税理士講座が5割免除でお得に受講できます。(※)
※大学院事務局の審査があり、また対象講座および免除率は変更となる可能性があります。